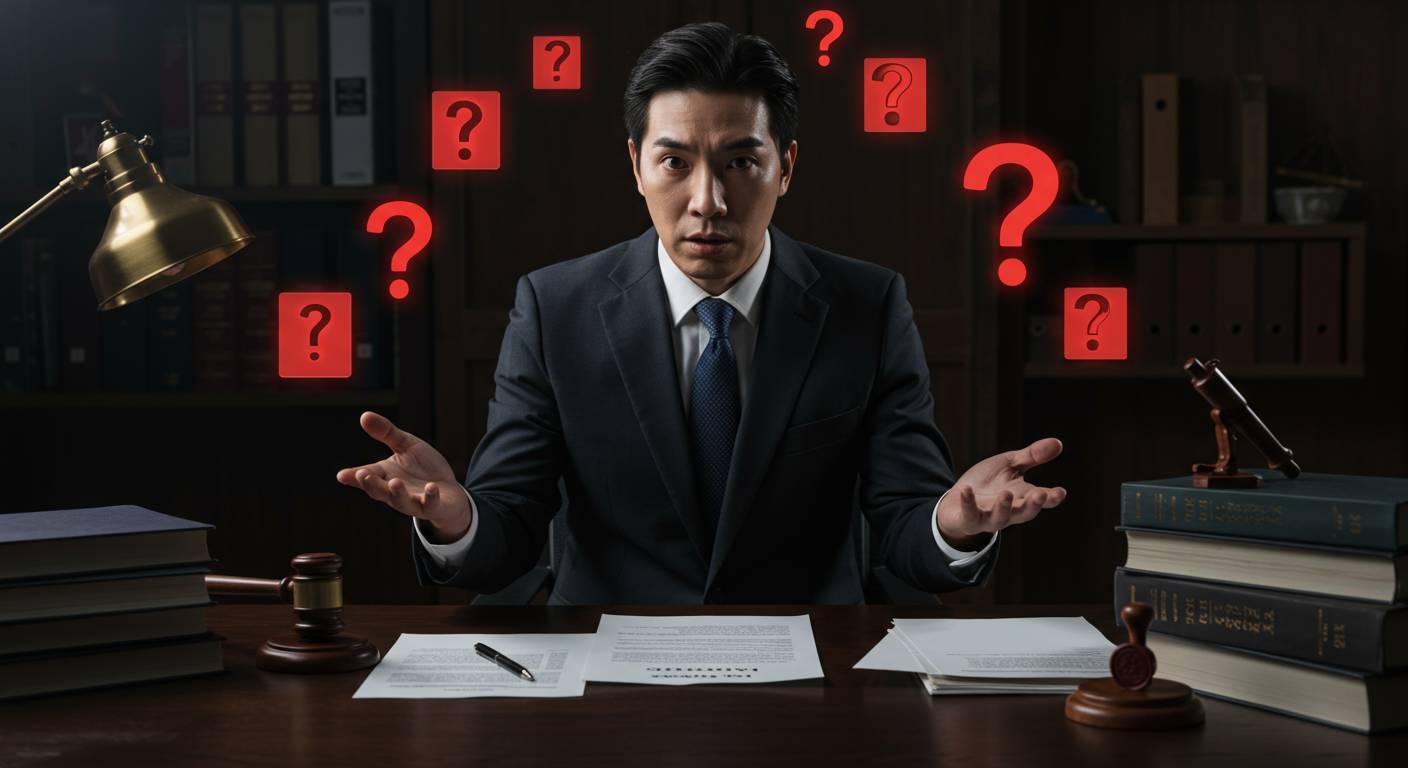
遺言書について「自分には関係ない」「まだ早い」と思っていませんか?実は多くの方が遺言書に関して重大な誤解を持ったまま、将来の不安を抱えています。特に子供がいない夫婦にとって、遺言書は想像以上に重要な役割を果たすものです。
先日、横浜市金沢区にお住まいの70代女性から「遺言公正証書を作成して本当に良かった」というお声をいただきました。この方は当事務所の遺言セミナーに参加されたことをきっかけに、ご夫婦で遺言書の重要性を実感され、公正証書の作成を依頼されたそうです。
「子供がいない私たち夫婦には、遺言書が非常に重要だと気づきました。公正証書の遺言書ができて本当に安心しています。遺言執行者にもなっていただき、心強く感じています」とのお言葉をいただきました。
このように、正しい知識を得ることで人生の不安が解消される瞬間を日々目の当たりにしています。この記事では、横浜の行政書士として長年遺言・相続に携わってきた経験から、多くの方が誤解している遺言書の"7つの致命的な誤解"について解説します。
相続で家族が争うことなく、大切な財産を確実に引き継ぐために必要な知識を、わかりやすくお伝えしていきます。特に子供がいないご夫婦や、将来の相続について不安をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。
コンテンツ
1. 行政書士が明かす「遺言書の致命的な誤解」―子供がいない夫婦が絶対知るべき真実
子供がいない夫婦の場合、「遺言書は必要ない」と考えていませんか?これは遺言書に関する最も危険な誤解の一つです。配偶者がすべての財産を相続できると思っている方が多いですが、法定相続では配偶者の相続分は2分の1に過ぎません。残りの財産は亡くなった方の両親や兄弟姉妹に分配されることになります。
例えば、5000万円の財産がある夫が亡くなった場合、妻が相続できるのは2500万円のみ。残りは夫の両親や兄弟姉妹の権利となります。この状況で自宅の名義が夫だけだった場合、妻は家に住み続けるために親族から持分を買い取る必要が生じることもあります。
さらに注意すべきは、配偶者以外の相続人が相続放棄をしなければ、自動的に共有名義となってしまう点です。故人の兄弟との関係が疎遠だった場合、突然連絡を取る必要が生じ、トラブルに発展するケースも珍しくありません。
実際、東京都内のAさん夫婦のケースでは、夫が突然他界した際、遺言書がなかったために夫の兄弟と遺産分割協議が必要となり、最終的に自宅の一部を売却せざるを得なくなりました。
遺言書があれば、「妻にすべての財産を相続させる」と明確に指定できます。公正証書遺言を作成すれば、検認手続きも不要で、相続手続きがスムーズに進みます。行政書士や弁護士などの専門家に相談し、正確な知識を得ることが重要です。子供がいなくても、大切な配偶者を守るための遺言書作成を検討してみてください。
2. 「遺言なんて必要ない」と思っていませんか?70代女性が語る公正証書作成で得た安心感
「私には財産がそれほどないから」「家族が仲良くしているから大丈夫」と、遺言書の作成を先送りにしていませんか?この考え方が、将来の家族トラブルの種になることをご存知でしょうか。
東京都在住の佐藤さん(仮名・75歳)は、夫を亡くした後、「子どもたちに迷惑をかけたくない」という思いから公正証書遺言を作成しました。
「最初は本当に必要かどうか迷いました。でも、知人が遺言なしで亡くなった後、残された家族が遺産分割で揉めている姿を見て、私は決断したんです」と佐藤さんは語ります。
実際、法務省の統計によれば、遺産分割の調停・審判の申立件数は年々増加傾向にあります。遺言書がない場合、相続人全員の合意が必要となり、一人でも反対すれば話し合いは難航します。
「兄弟仲が良くても、その配偶者が入ると話が変わることも多いんです」と、行政書士の田中事務所では説明しています。
佐藤さんのケースでは、自宅を長男に、預金を次男と長女に分ける内容の遺言を作成。「公正証書なら法的効力が確実で、紛失や偽造の心配もない」という点が決め手になったそうです。
遺言書作成の費用は、公正証書で平均5〜15万円程度。「高いと感じるかもしれませんが、遺言がないために起こる相続トラブルの解決費用と比べれば、むしろ家族への最後の思いやりです」と専門家は指摘します。
佐藤さんは「遺言書を作ってからは、本当に心が軽くなりました。これが私の子どもたちへの最後のプレゼントだと思っています」と微笑みます。
あなたも「まだ早い」「必要ない」と思っていませんか?遺言書は財産の多さではなく、残された家族の未来を守るためのものです。今日からでも、専門家に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。
3. 相続トラブルを未然に防ぐ!行政書士が警告する「遺言書の誤解」と正しい対策法
相続問題で家族が争うケースは後を絶ちません。法務省の統計によれば、相続に関する調停申立件数は毎年約8,000件にも上り、その多くが遺言書に関する誤解から生じています。行政書士の実務経験から見えてくる「遺言書の誤解」と、トラブルを防ぐための正しい対策をご紹介します。
最も多い誤解は「自筆証書遺言は自分で書けば問題ない」という思い込みです。実際には、民法で定められた形式に従わないと無効になるケースが多発しています。日付や署名・押印が不十分なだけでなく、相続財産の記載が不明確で紛争に発展するケースもあります。
また「公正証書遺言は費用がかかりすぎる」という誤解も危険です。確かに公証役場での手続きには手数料がかかりますが、自筆証書遺言が無効になったり、検認手続きに時間がかかったりするリスクと比較すると、実際には公正証書遺言のほうがコストパフォーマンスに優れていることが多いのです。
「一度作成したら終わり」という誤解も要注意です。相続財産や家族関係は時間とともに変化します。定期的に内容を見直さなければ、最新の状況を反映しない遺言書が残ってしまいます。不動産や預貯金などの資産状況が変わったときや、結婚・離婚・出産など家族構成に変化があったときには必ず見直しましょう。
さらに「自分の意思だけで財産を自由に分配できる」という誤解も多く見られます。実は民法では「遺留分」という制度があり、法定相続人の最低限の取り分が保証されています。この点を理解せずに遺言書を作成すると、死後に遺留分侵害額請求が行われ、トラブルの原因となります。
これらの誤解を避けるためには、専門家のサポートを受けることが最も確実です。東京都内の相続に強い法律事務所「弁護士法人リーガルフォレスト」や「行政書士法人みんなのみらい」などでは、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供しています。特に複雑な資産構成や家族関係がある場合は、早めの相談が望ましいでしょう。
相続トラブルを防ぐ最大の武器は「正しい知識」と「適切な準備」です。大切な家族が争うことのないよう、遺言書の正しい理解と作成を心がけましょう。
投稿者プロフィール

-
公正証書は、あなたの権利を守り、より良い人生を送るために作成するものです。
そのためには、まずプロに相談したいところです。
横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
法律業界30年以上の豊富な経験と実績を活かし最良の提案をします。
「話しやすく・親しみやすく・分かりやすい」をモットーに初回相談費用は無料です。
ちょっとした疑問でも、まずは電話かメールでぜひご相談ください。
最新の投稿
 遺言書2026年1月18日子どものいない夫婦の遺言書戦略!公正証書で財産を適切に分配
遺言書2026年1月18日子どものいない夫婦の遺言書戦略!公正証書で財産を適切に分配 離婚協議2026年1月17日女性必見!協議離婚で権利を守るための公正証書活用法と行政書士の役割
離婚協議2026年1月17日女性必見!協議離婚で権利を守るための公正証書活用法と行政書士の役割 公正証書・契約書2026年1月16日親の介護に備える!成年後見契約に使える公正証書作成の全知識
公正証書・契約書2026年1月16日親の介護に備える!成年後見契約に使える公正証書作成の全知識 公正証書・契約書2026年1月15日知らないと損する!事実婚カップルのための公正証書活用法
公正証書・契約書2026年1月15日知らないと損する!事実婚カップルのための公正証書活用法




