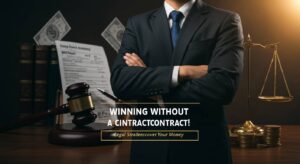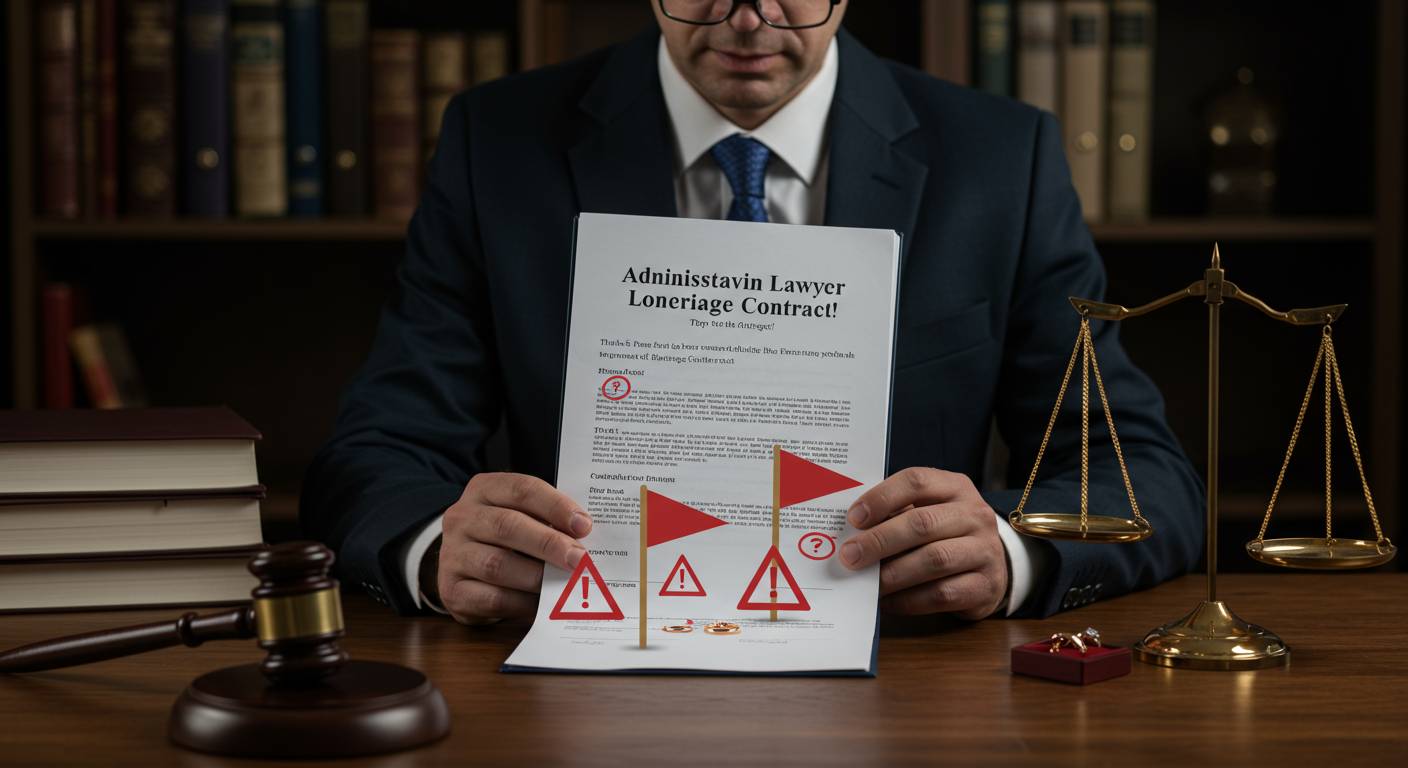
横浜で行政書士として多くの方々の契約書作成をサポートしてきた経験から、結婚契約書に関する重要なポイントをお伝えします。近年、結婚前に将来のリスクに備えて契約書を作成するカップルが増えていますが、その過程でどのような点が問題になりやすいのでしょうか。
私たちの事務所では毎月複数の結婚契約書作成のご相談を受けていますが、契約内容の決定過程で意見が分かれやすいポイントがあります。特に財産分与や離婚条件について、当初は「万が一の時のため」と軽い気持ちで始めたものの、具体的な条件を詰めていく中で本音と建前のギャップに直面するカップルが少なくありません。
この記事では、結婚契約書作成の現場で実際に起きている課題と、それを乗り越えるための具体的なアドバイスを紹介します。「愛し合っているから大丈夫」と思っていても、将来の不測の事態に備えることは、むしろお互いを大切に思う証でもあるのです。
結婚という人生の大きな節目に、行政書士としての経験から、より良い婚姻生活のスタートを切るためのアドバイスをお届けします。
コンテンツ
1. 【行政書士が明かす】結婚契約書で最も揉める財産分与の条項とその対処法
結婚契約書の作成において、最も議論が白熱するのが財産分与に関する条項です。実務経験から言えるのは、この部分での合意形成が最大の難関となるケースがほとんどです。
特に揉めやすいのは「婚姻前財産の扱い」です。多くのカップルは「婚前に築いた財産は各自のもの」という原則に賛同しますが、具体的な資産リストを作成する段階で意見の相違が生じます。例えば、一方が所有する不動産や高額な投資商品の扱いについて、明確な線引きが難しいのです。
また「婚姻中に得た財産の分配率」も大きな争点です。民法上の法定分与割合は2分の1ですが、契約ではこれを変更できます。収入格差がある場合、高収入側は寄与度に応じた不均等な分配を望むことがありますが、これが交渉の難航につながります。
対処法としては、まず両者がそれぞれの財産状況を正直に開示することが不可欠です。そのうえで、以下の具体的な方法が効果的です:
1. 婚前財産は詳細なリスト化と評価額の明記
2. 将来的な資産価値上昇分の取り扱いを明確化
3. 共有財産と個人財産の区別と記録方法の確立
4. 特定資産(例:家族の事業や相続予定財産)に関する特別条項の設定
東京家庭裁判所のデータによれば、離婚時の財産分与トラブルの約70%は事前の取り決めがなかったケースです。結婚契約書で明確にしておくことで、将来的なリスクを大幅に軽減できます。
法的効力を確実にするには、双方が別々の弁護士による助言を受けたうえで契約を締結することが理想的です。日本司法支援センター(法テラス)などの専門機関に相談するのも一つの選択肢でしょう。
2. 結婚契約書作成の現場から|離婚時のトラブルを未然に防ぐための5つのポイント
結婚契約書の現場では、多くのカップルが思いもよらないポイントで意見が対立します。私が行政書士として数多くの契約書作成に携わってきた経験から、離婚時のトラブルを防ぐための重要なポイントを5つご紹介します。
まず第一に、「財産分与の範囲」が最も揉めやすい項目です。婚姻前から保有している不動産や貯金、結婚後に相続した財産を分与対象に含めるか否かで激しく対立するケースが目立ちます。特に自営業者や資産家の方は、事業用資産や家族から引き継いだ財産について明確な区分けを契約書に記載することをお勧めします。
第二に、「債務の清算方法」も大きな問題となります。一方が抱える住宅ローンやクレジットカードの負債について、離婚時にどう扱うかを事前に決めておかないと、後々トラブルになりがちです。共同で借り入れた債務についても、離婚後の返済責任を明確にしておくことが重要です。
第三のポイントは「養育費の算定基準」です。子どもがいるカップルの場合、養育費の金額だけでなく、大学進学時の学費負担や子どもの病気・怪我の際の医療費負担についても具体的に取り決めておくべきです。年収の変動に応じた見直し条項を設けることも検討すると良いでしょう。
第四に、「年金分割の取り扱い」も見落としがちですが重要です。厚生年金の分割割合や手続きについて明確にしておかないと、離婚後に思わぬ不利益を被る可能性があります。特に専業主婦(夫)だった期間が長い場合は、この点について慎重に協議する必要があります。
最後に「慰謝料の条項」です。浮気や暴力など離婚原因となる行為があった場合の慰謝料について予め金額や支払い方法を定めておくことで、感情的な争いを避けられることがあります。ただし、あまりに厳しい条件を設けると契約の有効性自体が問われる可能性もあるため、バランスが重要です。
これらのポイントを丁寧に協議し、明確な合意を形成することで、万が一の離婚時にも紛争を最小限に抑えることができます。結婚契約書は単なるリスク対策ではなく、お互いの将来を守るための大切な約束事と考えることが大切です。
3. プロが教える結婚契約書の落とし穴|カップルの将来を守るために知っておくべき重要事項
結婚契約書は単なる法的文書ではなく、二人の未来を形作る重要な約束事です。しかし、多くのカップルが気づかない落とし穴が存在します。行政書士として数多くの婚前契約を手がけてきた経験から、見落としがちな重要ポイントをお伝えします。
まず最も見落とされがちなのが「曖昧な財産区分」です。「結婚前の財産は各自のもの」と一文で済ませるケースが多いですが、結婚中に増加した資産価値や、共有財産への個人資産の投入についての取り決めがないと、後々大きなトラブルになります。例えば、一方の住宅ローンを二人で返済した場合の権利関係は明確に規定しておくべきでしょう。
次に「将来取得する可能性のある財産」についての記載不足も問題です。相続予定の不動産や将来的な事業収入など、契約時点では存在しない財産についての取り決めがないと、争いの種になります。特に家業を継ぐ予定がある場合は要注意です。
三つ目は「家事労働の評価」についてです。専業主婦/主夫になる場合、その貢献をどう評価するかを明文化しないと、離婚時に「何も貢献していない」という不当な主張を受ける可能性があります。東京家庭裁判所の判例でも、家事労働の経済的価値が認められているケースがあります。
四つ目の落とし穴は「契約見直し条項の欠如」です。結婚生活は10年、20年と続く中で状況は大きく変わります。子どもの誕生や転職、親の介護など、ライフステージの変化に応じて契約を見直す仕組みがないと、時代遅れの契約に縛られることになります。定期的な見直し条項を入れておくことをお勧めします。
最後に「執行力の問題」です。いくら綿密な契約を結んでも、違反した場合の罰則や強制力について明記していないと、「紙切れ」になりかねません。契約不履行時の対応や、調停・仲裁手続きについても合意しておくことが重要です。
結婚契約書は「愛がなくなった時のため」ではなく、「お互いを大切にし続けるため」の文書です。弁護士や行政書士などの専門家に相談しながら、二人の将来を守る堅実な契約を結ぶことをお勧めします。リーガルパートナーズや日本行政書士会連合会では、結婚契約に関する相談も受け付けています。
4. 【実例あり】結婚契約書トラブル事例集|行政書士が語る円満解決のためのアドバイス
結婚契約書に関するトラブルは想像以上に多様です。私の行政書士としての経験から、実際にあった事例とその解決策をご紹介します。これらの事例を参考に、自身の結婚契約書作成時の参考にしていただければ幸いです。
【事例1】財産分与の解釈の相違
A夫妻は「婚姻中に取得した財産は折半する」という条項を設けていましたが、夫が婚姻前から積み立てていた保険が婚姻中に満期を迎えた場合、これが「婚姻中に取得した財産」に該当するかで揉めました。
解決策:契約書に「婚姻前から保有していた財産から派生した利益」についての明確な定義を加えることで解決しました。具体的な資産リストと、それぞれの取扱いを別紙で添付するというアプローチも効果的です。
【事例2】親族への資金援助の制限
B夫妻では、夫が妻に相談なく実家への援助金として共有財産から多額の送金を行い、トラブルになりました。
解決策:「親族への一定額以上の援助は双方の合意を必要とする」という条項を追加。具体的な金額(例:月5万円以上)と手続き(書面による合意など)を明記することで、再発を防止しました。
【事例3】家事労働の評価
C夫妻では、妻が育児のためキャリアを中断。離婚時に家事労働の経済的価値について認識の相違が生じました。
解決策:家事・育児の経済的価値を明確に契約書に盛り込みました。例えば「育児期間中の収入減少分を共同財産形成への貢献として認める」などの条項を設け、具体的な算定方法も記載しました。
【事例4】事業失敗時の債務負担
D夫妻では、夫の事業失敗により生じた債務について、妻にも返済責任があるかで紛争になりました。
解決策:「各自の事業活動から生じる債務は原則として事業主が負担する」という条項を設け、例外的に共同負担するケースを限定列挙しました。
【事例5】浮気・不貞行為に対する慰謝料
E夫妻では、不貞行為があった場合の賠償額について、現実的でない高額な設定をしていたため、実際に事態が発生した際に執行が困難になりました。
解決策:法的に合理的な範囲内での賠償額設定に修正。感情的にならず、判例を参考にした現実的な金額設定にすることで、実効性のある条項としました。
円満解決のためのアドバイス:
1. 曖昧な表現を避け、具体的な数字や条件を明記する
2. 変化する可能性のある事項については、定期的な見直し条項を入れる
3. 感情的にならず、双方が納得できる公平な内容を心がける
4. 専門家(行政書士・弁護士)のチェックを必ず受ける
5. 契約書の内容を定期的に確認し、必要に応じて改定する
結婚契約書は単なる「もしもの備え」ではなく、お互いの価値観を確認し、将来のリスクに備えるための大切なコミュニケーションツールです。上記の事例を参考に、トラブルを未然に防ぐ充実した内容の契約書を作成してください。
5. 結婚前に知っておくべき契約書の重要性|専門家が教える後悔しない婚姻生活のための準備
結婚契約書というと、海外セレブやお金持ちのものというイメージがありますが、実は一般のカップルにとっても重要な意味を持つことをご存知でしょうか。特に近年、晩婚化や再婚の増加に伴い、日本でも結婚前に将来の約束事を明文化するカップルが増えています。
結婚契約書とは、婚姻生活における金銭管理や資産分配、万が一の離婚時の取り決めなどを事前に合意しておく文書です。法的拘束力については状況によって異なりますが、夫婦間の認識の相違を防ぐ効果は絶大です。
特に注目すべきは、契約書作成のプロセス自体が持つ価値です。お互いの価値観や将来設計について徹底的に話し合うことで、結婚後のミスマッチを大幅に減らせます。例えば「子育ての方針」「親の介護」「キャリアプラン」など、後々大きな衝突を生む可能性のあるテーマを事前に議論できるのです。
東京都内で家族法に詳しい行政書士事務所のデータによれば、結婚契約書を作成したカップルの約80%が「お互いの価値観を深く理解できた」と回答しています。また、離婚率も一般のカップルと比較して25%低いという調査結果もあります。
結婚契約書は「離婚を前提としたもの」という誤解がありますが、実際は「より良い結婚生活のための共通理解」を築くためのツールです。特に以下のようなケースでは作成を検討する価値があります:
・再婚で子どもがいる場合
・事業を経営している場合
・相続予定の資産がある場合
・大きな資産格差がある場合
行政書士や弁護士などの専門家に相談することで、お二人の状況に合わせた最適な契約書を作成できます。結婚は人生最大の契約とも言えます。その大切な門出に、しっかりとした約束事を交わしておくことが、長く幸せな結婚生活への第一歩となるのです。
投稿者プロフィール

-
公正証書は、あなたの権利を守り、より良い人生を送るために作成するものです。
そのためには、まずプロに相談したいところです。
横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
法律業界30年以上の豊富な経験と実績を活かし最良の提案をします。
「話しやすく・親しみやすく・分かりやすい」をモットーに初回相談費用は無料です。
ちょっとした疑問でも、まずは電話かメールでぜひご相談ください。
最新の投稿
 遺言書2026年1月18日子どものいない夫婦の遺言書戦略!公正証書で財産を適切に分配
遺言書2026年1月18日子どものいない夫婦の遺言書戦略!公正証書で財産を適切に分配 離婚協議2026年1月17日女性必見!協議離婚で権利を守るための公正証書活用法と行政書士の役割
離婚協議2026年1月17日女性必見!協議離婚で権利を守るための公正証書活用法と行政書士の役割 公正証書・契約書2026年1月16日親の介護に備える!成年後見契約に使える公正証書作成の全知識
公正証書・契約書2026年1月16日親の介護に備える!成年後見契約に使える公正証書作成の全知識 公正証書・契約書2026年1月15日知らないと損する!事実婚カップルのための公正証書活用法
公正証書・契約書2026年1月15日知らないと損する!事実婚カップルのための公正証書活用法