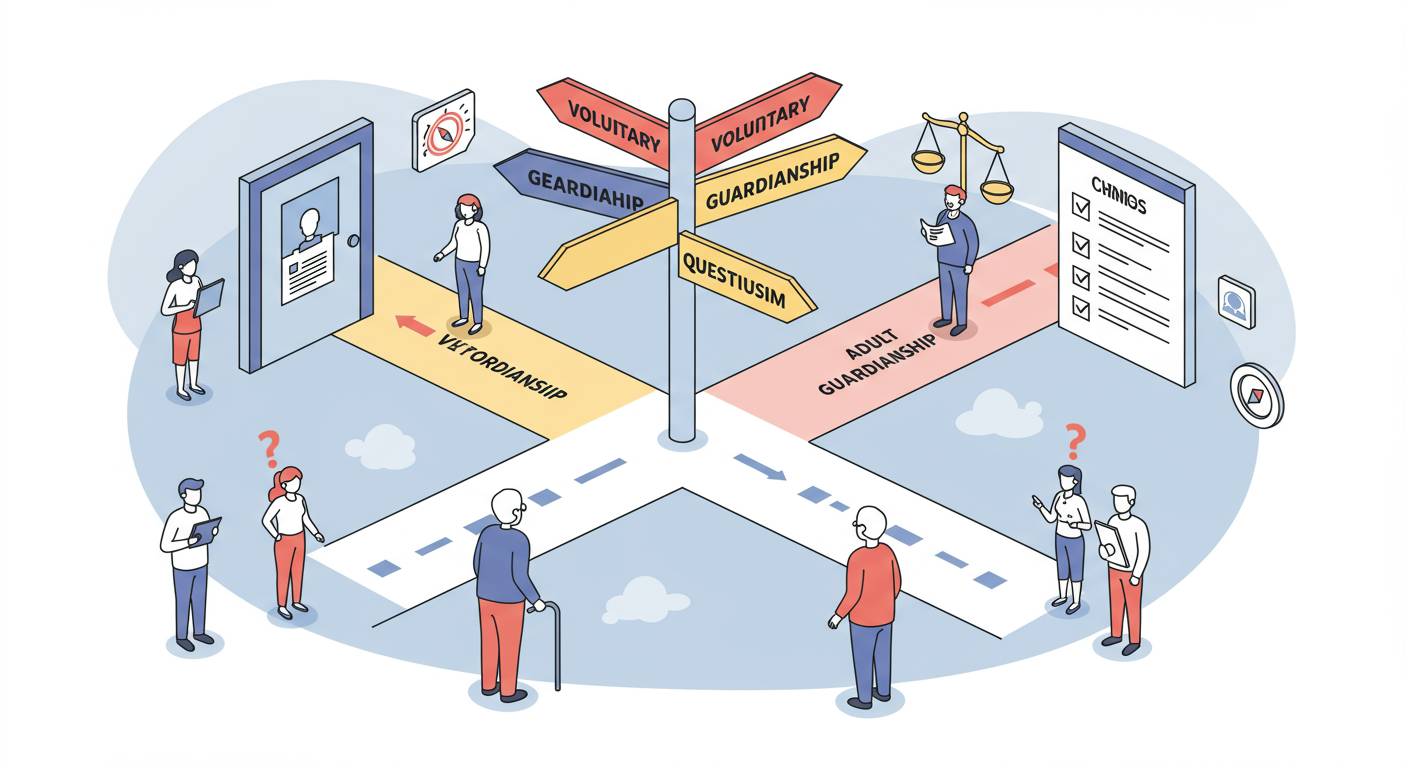
こんにちは。行政書士法人コウセイ総合事務所横浜オフィスです。
「将来、判断能力が低下したときのことを考えておきたい…」
「親が高齢になってきて、後見制度について知りたい…」
そんな悩みをお持ちの方は少なくないのではないでしょうか。
先日、70代のAさんが当事務所に相談にいらっしゃいました。「認知症の母のために成年後見制度を利用したいが、自分自身の将来のためには何を準備すればいいのか」というご相談でした。
母親のケースでは成年後見制度が適していましたが、Aさん自身はまだお元気なうちから準備できる任意後見制度の方が適していることをご説明しました。このようなケースは非常に多く、後見制度には「成年後見」と「任意後見」の2種類があることを初めて知る方がほとんどです。
どちらを選ぶかで将来の生活の質が大きく変わることもあります。この記事では、実際の相談事例をもとに、任意後見と成年後見の違いや、あなたに合った制度の選び方をわかりやすくご紹介します。
「自分の意思を尊重してほしい」「家族に負担をかけたくない」「財産管理を安心して任せたい」など、あなたの希望によって最適な選択は変わります。ぜひ最後までお読みいただき、将来への備えの第一歩としてください。
コンテンツ
1. 「任意後見と成年後見の決定的な違い!自分に合う制度がわかる5つのチェックポイント」
「親が認知症になった時のこと」「自分の将来に備えたい」と考えたとき、後見制度の存在を知っても「任意後見」と「成年後見」の違いがわからず悩む方は多いものです。実はこの2つ、開始時期や本人の意思尊重において大きな違いがあります。今回は、あなたに合った後見制度を選ぶための5つのチェックポイントをご紹介します。
【チェックポイント1】判断能力が現在あるかどうか
任意後見制度は、契約時点で本人に十分な判断能力が必要です。将来の認知症などに備えて「今のうちに準備しておきたい」という方に適しています。一方、成年後見制度は、すでに判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申立てて開始する制度です。
【チェックポイント2】自分で後見人を選びたいか
任意後見では契約で自分の信頼する人(家族・専門家など)を後見人に指定できます。成年後見では家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも希望通りにはなりません。「この人に頼みたい」という明確な意向がある場合は任意後見が適しています。
【チェックポイント3】費用の違いを重視するか
任意後見は公正証書作成費用(約1〜2万円)と後見監督人への報酬(月額2万円前後)がかかります。成年後見は申立費用(約5万円程度)と後見人への報酬(月額2万円前後)が必要です。長期的に見ると大きな差はないものの、発生時期が異なります。
【チェックポイント4】後見人の権限範囲の自由度
任意後見では契約で後見人の権限を自由に設定できます。例えば「財産管理のみ」「身上監護のみ」といった限定が可能です。成年後見では法律で定められた権限が一律に与えられるため、自分の希望に沿った柔軟な設計をしたい場合は任意後見が優位です。
【チェックポイント5】開始までの時間的余裕
成年後見は申立てから開始まで通常2〜3ヶ月かかります。対して任意後見は契約後すぐに発効するわけではなく、将来判断能力が低下した時点で「任意後見監督人選任の申立て」を行う必要があります。この申立てから実際に任意後見が始まるまでも同様に時間がかかるため、緊急性がある場合の対応には注意が必要です。
これら5つのポイントを踏まえると、「今はまだ元気で、将来に備えて自分の意思を尊重した後見制度を準備したい」という方には任意後見が、「すでに判断能力が低下している、または急速に低下しつつある家族のために早急に後見人を立てたい」という方には成年後見制度が適していると言えるでしょう。
実際には、任意後見契約と併せて「見守り契約」や「財産管理等委任契約」を結ぶことで、判断能力低下の初期段階からサポートを受けられる包括的な対策を取ることも可能です。自分や家族の状況に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら最適な制度を選びましょう。
2. 「プロが教える!任意後見と成年後見、選び方で後悔しないための完全ガイド」
将来の不安に備えて後見制度を検討しているものの、「任意後見」と「成年後見」の違いがわからず、選択に迷っていませんか?この選択は将来の生活や財産管理に大きく影響するため、慎重に検討する必要があります。
法律の専門家である司法書士の間では「適切な後見制度の選択が、その後の人生の質を大きく左右する」と言われています。実際、日本司法書士会連合会の調査によると、後見制度を利用している人の約70%が「事前に十分な情報を得ていれば、異なる選択をしていた可能性がある」と回答しています。
まず基本的な違いを押さえましょう。任意後見制度は、判断能力があるうちに自分で後見人を指定し、将来判断能力が低下した時に発効する制度です。一方、成年後見制度は、すでに判断能力が低下している方のために家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
任意後見制度のメリットは、自分の希望を反映した後見人を選べること、発効のタイミングを柔軟に決められることです。例えば、信頼する親族や長年付き合いのある弁護士を指定できます。しかし、事前の契約が必要なため、判断能力があるうちに準備しておく必要があります。
一方、成年後見制度は申立てがあれば比較的速やかに開始できますが、後見人は裁判所が選任するため、必ずしも本人の希望通りにならない可能性があります。また、権限の範囲も法律で定められており、カスタマイズの余地が少ないのが特徴です。
どちらを選ぶべきか迷った場合は、以下の点を考慮するとよいでしょう:
1. 現在の判断能力:すでに判断能力に不安がある場合は成年後見が適している
2. 信頼できる後見人候補の有無:身近に信頼できる人がいれば任意後見が有利
3. 財産管理の複雑さ:資産が複雑な場合、専門的知識を持つ後見人が必要
4. 自分の意思の反映度:自分の希望を細かく反映させたい場合は任意後見が適している
東京司法書士会の相談窓口担当者は「後見制度は一度始まると簡単に変更できないため、専門家に相談しながら慎重に選ぶことが重要」と強調しています。実際に制度を利用している方々からは「早めに準備していて良かった」という声が多く聞かれます。
最終的な選択の前に、法テラスや各地の司法書士会が実施している無料相談会を利用して、専門家の意見を聞くことをおすすめします。あなたの状況に合った最適な選択ができるよう、十分な情報収集と検討を行いましょう。
3. 「今すぐできる!任意後見と成年後見の簡単診断テスト〜将来の安心を手に入れる最適な選択〜」
将来の不安を解消するためには、自分に合った後見制度を選ぶことが重要です。以下の質問に「はい」か「いいえ」で答えて、あなたに最適な選択肢を見つけましょう。
【診断テスト:5つの質問】
Q1. 現在、判断能力は十分にありますか?
Q2. 将来のケアについて、特定の人に任せたい希望がありますか?
Q3. 財産管理だけでなく、医療や介護についても自分の意思を尊重してもらいたいですか?
Q4. 費用をできるだけ抑えたいと考えていますか?
Q5. 契約内容を自分で決めたいと思いますか?
【診断結果の見方】
■「はい」が3つ以上:任意後見制度がおすすめ
任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来の不安に備えて自分で後見人を選び、サポート内容を決められる制度です。自己決定権を最大限に尊重したい方に適しています。
東京都内の司法書士法人みらいでは「将来に備える任意後見契約は60代からの準備が理想的」とアドバイスしています。
■「いいえ」が3つ以上:成年後見制度がおすすめ
成年後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態になっている方や、親族などからの申立てで後見人が選任される制度です。家庭裁判所が選任するため、中立的な立場の専門家がサポートしてくれます。
【重要ポイント】
・任意後見は「事前の備え」、成年後見は「事後の対応」という違い
・任意後見なら自分で後見人を選べるが、成年後見は裁判所が決定
・費用面では任意後見のほうが契約内容によってカスタマイズ可能
診断結果に迷った方は、最寄りの弁護士会や司法書士会、社会福祉協議会などの無料相談窓口を利用してみましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な選択ができます。
投稿者プロフィール

-
公正証書は、あなたの権利を守り、より良い人生を送るために作成するものです。
そのためには、まずプロに相談したいところです。
横浜駅西口の公正証書作成オフィスである保坂一成事務所では、書類作成の専門家が効力のある書面作りを行っています。
法律業界30年以上の豊富な経験と実績を活かし最良の提案をします。
「話しやすく・親しみやすく・分かりやすい」をモットーに初回相談費用は無料です。
ちょっとした疑問でも、まずは電話かメールでぜひご相談ください。
最新の投稿
 遺言書2026年1月18日子どものいない夫婦の遺言書戦略!公正証書で財産を適切に分配
遺言書2026年1月18日子どものいない夫婦の遺言書戦略!公正証書で財産を適切に分配 離婚協議2026年1月17日女性必見!協議離婚で権利を守るための公正証書活用法と行政書士の役割
離婚協議2026年1月17日女性必見!協議離婚で権利を守るための公正証書活用法と行政書士の役割 公正証書・契約書2026年1月16日親の介護に備える!成年後見契約に使える公正証書作成の全知識
公正証書・契約書2026年1月16日親の介護に備える!成年後見契約に使える公正証書作成の全知識 公正証書・契約書2026年1月15日知らないと損する!事実婚カップルのための公正証書活用法
公正証書・契約書2026年1月15日知らないと損する!事実婚カップルのための公正証書活用法




